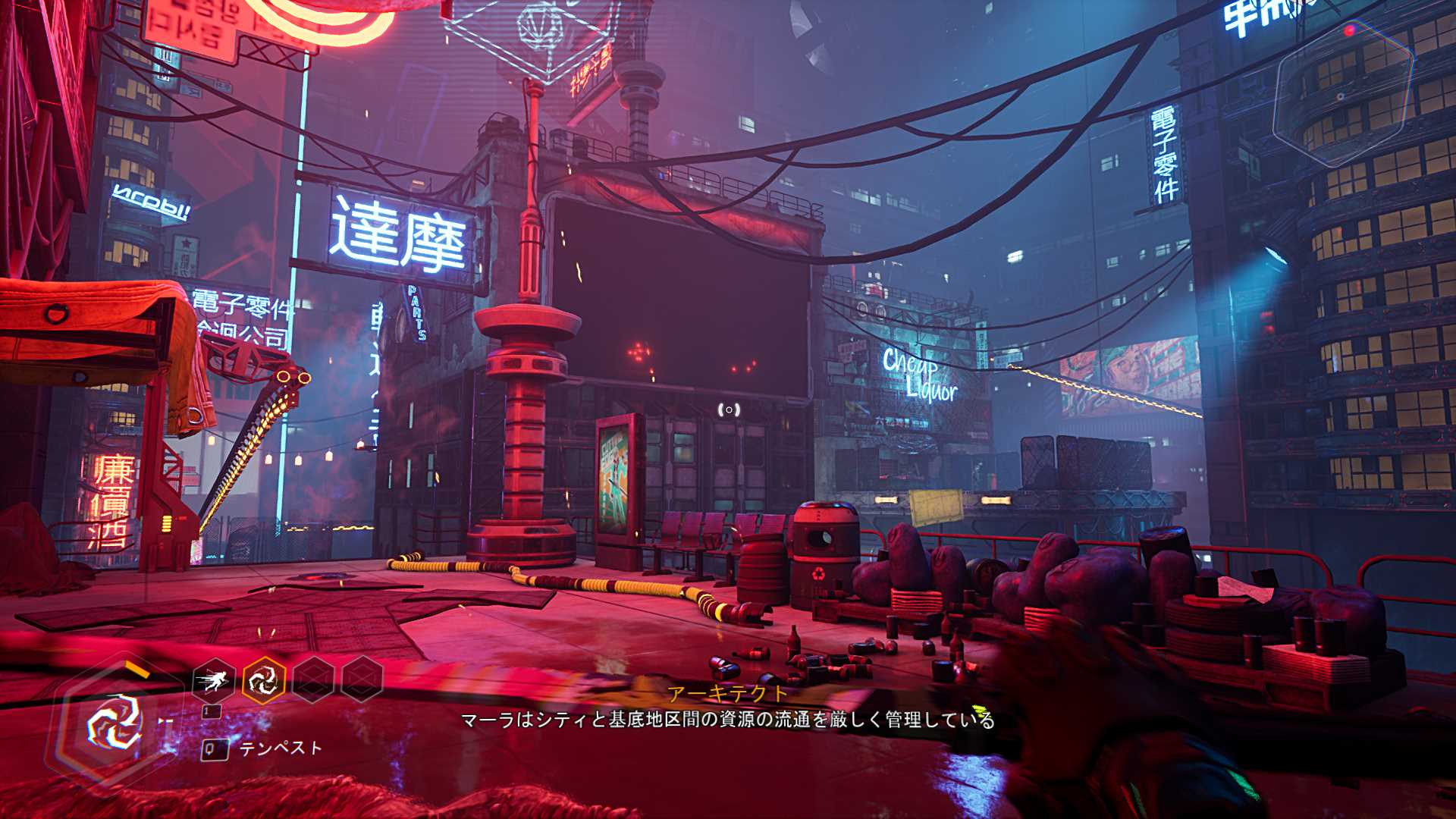単純に昔の名作FPSのシステムをそのまま持ってきて沢山長く遊べるようにしただけだと、ゲームとしてはつまらないものになるという代表的な失敗例と呼んで差し支えないと思う。流石に1マップ40分とか単純に長すぎ。ストーリー性のあるFPSで演出込みで40分なら分かるけど、40分間ひたすら探索&銃撃だけだと中弛みが半端ない。かといって短すぎるとそれはそれで価格に見合ったボリュームじゃないと大批判を受ける(Shadow Warrior3みたいな)ので、1ステージの長短って繊細な問題なんだなと再認識させられた。

ボス戦はギミック
1stボスは普通にダメージを重ねると塔の上層へ移動するので空中浮遊にSigilを使って2Fに移動して追加ダメージを与えたら倒せる。遮蔽物多めなので撃って隠れる基本的な反復動作の確認。
2ndボスは最初は無敵状態のボスの攻撃を回避しながらSigilを利用して不可視の階段を見えるようにして最奥のレバーを押して廻る。すべてのレバーを押すと塔の最上層に場面転換するので外周をフワフワ漂い続けるボスの攻撃から柱を盾にして合間に攻撃を加えていく第二段階が始まる。これまで盾になっていた石柱が全て倒壊するが中央のSigilを使うとEthrealの柱が浮き上がるのでこの時限付遮蔽物を盾として使う。
Finalボスはボス戦が始まるとボスが4つの像のある台に歩いて行くので追跡していきボスが召喚モーションを取っている間に台座の赤いコアを撃ち抜いていく。撃ち抜くのが間に合わないと大量の雑魚mobが呼び出されるのでどんどん苦しくなるので最優先はコアの破壊。全てのコアを破壊し尽くすと中央にボスが移動するので第二段階が始まる。遮蔽物やバリアのアーティファクトを使いながらボスの攻撃を回避しつつダメージを重ねると最後にボスが特大の範囲攻撃をばら撒いて死亡する。最後はボスのいたところに開通するポータルを潜るとエンディング
ラスボスをブレードとメイスだけで倒すという実績があるんだけど、これどうやったら達成できるのか謎。コアの撃ち抜きに射撃系武器の使用不可ってかなり条件厳しくない?